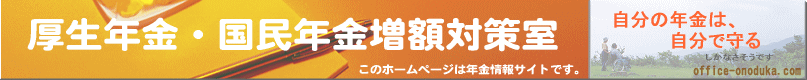
厚生年金・国民年金増額対策室 > 年金、みんな怒!(バック) > 第33号 年金の「見える目減り」「見えない目減り」「実質目減り」
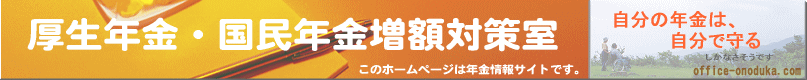
┏━━ ● 年金、みんな怒っています! ● 第33号 ◎ 年金の「見える目減り」「見えない目減り」「実質目減り」 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【 平成31年1月31日版 第33号 】 今回は、年金の目減りについてのお話です。 年金の目減りには、年金改定率がマイナスである場合の見える目減りだけでは なく、物価を改定率が下回る場合における見えない目減りもあります。 ・「見える目減り」…マイナスの時の年金改定率。通常は実質的な目減りになる が、改定率▲0.1%で物価変動率▲0.1%の時など、表面上はマイナスだが、 実質的な目減りがない場合もある。 ・「見えない目減り」…「年金改定率<物価変動率」の差で改定率分を除いた分 。改定率がプラスの場合、表面上はプラスだが実質的には目減りとなる。 ・「実質目減り」…年金の価値の減少。 発表されたばかりの平成31年度(2019年度)の年金改定でみると、 ・平成31年度(2019年度)の年金改定率→△0.1% ・物価変動率→△1.0% よって ・「見える目減り」…なし ・「見えない目減り」…▲0.9% ・「実質目減り」…▲0.9% また、違うパターンで、平成26年度(2014年度)の年金改定をみると、 ・平成26年度(2014年度)の年金改定率→▲0.7% ・物価変動率→△0.4% よって ・「見える目減り」…▲0.7% ・「見えない目減り」…▲0.4% ・「実質目減り」…▲1.1% となります。 下記は、直近6年の推移です。 平成26年度改定…年金改定率▲0.7% 物価変動率△0.4% 平成27年度改定…年金改定率△0.9% 物価変動率△2.7% 平成28年度改定…年金改定率△0.0% 物価変動率△0.8% 平成29年度改定…年金改定率▲0.1% 物価変動率▲0.1% 平成30年度改定…年金改定率△0.0% 物価変動率△0.5% 平成31年度改定…年金改定率△0.1% 物価変動率△1.0% 「見える目減り」「見えない目減り」「実質目減り」 平成26年度改定…「▲0.7%」「▲0.4%」「▲1.1%」 平成27年度改定…「プラス」「▲1.8%」「▲1.8%」 平成28年度改定…「据え置き」「▲0.8%」「▲0.8%」 平成29年度改定…「▲0.1%」「なし」「なし」 平成30年度改定…「据え置き」「▲0.5%」「▲0.5%」 平成31年度改定…「プラス」「▲0.9%」「▲0.9%」 直近6年間の合計は、 ・「見える目減り」…なし(△0.2%) ・「見えない目減り」…▲4.4% ・「実質目減り」…▲5.1% このように、直近では、年金改定率の変化がほとんどない一方で、物価と改定率 の差である「見えない目減り」は進んでおり、実質的な目減りが進行しているこ とがわかります。 しかし、それでもまだ本番前です。 これから本格化する年金の目減りについて、3点取り上げます。 ●年金目減り1…「マクロ経済スライド」は「見えない目減り」発生装置 年金給付を抑制する仕組みである平成16年度導入の「マクロ経済スライド」。 本来ならば、毎年度定められた「調整率」を年金改定率から差し引き給付抑制を はかるべきところ、年金改定がマイナスになる年度においては適用がないという 縛りがあるために、平成16年度から平成29年度の改定まで、その適用はわずか 1回しかありませんでした。 【マクロ経済スライドの適用の有無】 平成17年(2005年)4月~ 適用なし 平成18年(2006年)4月~ 適用なし 平成19年(2007年)4月~ 適用なし 平成20年(2008年)4月~ 適用なし 平成21年(2009年)4月~ 適用なし 平成22年(2010年)4月~ 適用なし 平成23年(2011年)4月~ 適用なし 平成24年(2012年)4月~ 適用なし 平成25年(2013年)4月~ 適用なし 平成26年(2014年)4月~ 適用なし 平成27年(2015年)4月~ ▲0.9% 平成28年(2016年)4月~ 適用なし 平成29年(2017年)4月~ 適用なし (関連)マクロ経済スライドが完全に発動されていたら ----------------------------------- 会計検査院が平成30年11月9日に公表した「平成29年度決算検査報告」の概要に よると、 『16年度以降、マクロ経済スライドを毎年度完全に発動したと仮定した場合、 28年度の給付水準は、実際の給付水準に対し、5.0ポイント低い試算結果となり 、これに基づく基礎年金国庫負担分相当額と実際の額との差額は、28年度までの 累計で3.3兆円(機械的試算)となる』 http://www.jbaudit.go.jp/report/new/summary29/pdf/fy29_tokutei_01.pdf (390ページより抜粋) ----------------------------------- しかし、マクロ経済スライドはすでに法改正されており、 平成30年度(2018年度)からは適用できなかった年度の「調整率」を翌年度以降に キャリーオーバーできるようになりました。 それが思惑通りに進んだのが、平成30年度~平成31年度の年金改定です。 平成30年(2018年)4月~ 適用なし(キャリーオーバー▲0.3%) 平成31年(2019年)4月~ ▲0.5%(30年度分▲0.3%+31年度分▲0.2%) 平成31年度(2019年)の年金改定率「△0.1%」は、本来ならば△0.6%の改定率と すべきところ、マクロ経済スライドの仕組みにより▲0.5%減らされて△0.1%と なりました。 マクロ経済スライドは、改定をマイナスにしないということで「見える目減り」 は増えませんが、キャリーオーバーの新ルールにより、以前よりも着実に 「見えない目減り」が増えていくことになります。 ●年金目減り2…改定率決定の2つのルール変更で「見える目減り」も増える これは、2021年度からの話です。 年金改定のルールでは、原則として賃金変動(=名目手取り賃金変動率)と 物価変動(=物価変動率)の低い方の改定となります。 しかし、現行では、賃金(マイナス)<物価(プラス)の場合、マイナスの改定 にはせずに「据え置き」とされます。 例えば、平成30年度の改定における物価変動率は「0.5%」でしたので、 名目手取り賃金変動率「▲0.4%」との比較で低い方の「▲0.4%」で改定すべ きところ、平成30年度の改定は「据え置き」とされました。 それが、(平成33年度)2021年度からは、賃金変動に合わせる考えが徹底され、 平成30年度改定のような事例では「▲0.4%」のマイナス改定となり、 「見える目減り」も増えることになります。 また、もう一つは、 賃金(マイナス)<物価(マイナス) の場合です。 この場合、現行では、低い方の賃金変動ではなく高い方の物価変動でマイナス 改定されることになっていますが、これも賃金変動に合わせたマイナス改定へと 変わります。 例えば、平成29年度の改定における物価変動率は「▲0.1%」でしたので、 名目手取り賃金変動率「▲1.1%」との比較で低い方の「▲1.1%」で改定すべ きところ、平成29年度の改定は高い方の物価変動率「▲0.1%」での改定となり ました。 それが(平成33年度)2021年度からは、賃金変動に合わせる考えが徹底され、 平成29年度改定のような事例では「▲1.1%」のマイナス改定となります。 これらの改定ルールの変更で、今後は「見える目減り」となるマイナス改定が 増えることになります。 ----------------------------------- (参考外部リンク) 日本年金機構:【年金額の改定ルールの見直し(平成33年4月~)】 https://www.nenkin.go.jp/ faq/jukyu/kyotsu/gakukaitei/201805-8.files/D.pdf ----------------------------------- ●年金目減り3…消費税率引き上げによる年金「目減り」の影響は「2~4年後」 平成26年(2014年)4月に消費税率が5%→8%となりました。 これにより、次年度の改定における物価変動率の数値は、 平成27年度(2015年度)→△2.7% となり、賃金変動率との差が大きくなるかと思いきや、 賃金変動率→△2.3%となりました。 年金改定での賃金変動率の計算には前年の物価変動率の数値が組み入れら れているために、消費税率の引き上げがあっても、それがすぐに年金目減りとは ならないのです。 しかし、消費税率の引き上げによる大きな物価変動率は、2~4年後の賃金変動率 の計算の数値を低くしますので、結果的に年金の目減りを促進します。 ここでいう賃金変動率は「名目手取り賃金変動率」といいますが、 計算中で2年前~4年前の実質賃金変動率(賃金変動率/物価変動率)の平均を 使用しますので、分母である物価変動率が大きいということは、 実質賃金変動率の下押しとなるのです。 2014年度(平成26年度)の消費税率引き上げで言えば、物価上昇2.7%を遠因に ・2016年度(平成28年度)実質賃金上昇率▲0.8%(平成24~26年度の平均) ・2017年度(平成29年度)実質賃金上昇率▲0.8%(平成25~27年度の平均) ・2018年度(平成30年度)実質賃金上昇率▲0.7%(平成26~28年度の平均) となり、その結果として名目手取り賃金変動率を押し下げたのです。 ----------------------------------- ※名目手取り賃金変動率の計算例(平成30年度の年金改定) 実質賃金変動率(2~4年度前の平均=平成26~28年度の平均)▲0.7% + 物価変動率(1年前のCPI(総合)の値)0.5% + 可処分所得割合変化率(3年度前の変化率)▲0.2% ▲0.7%+0.5%+▲0.2%=▲0.4% ----------------------------------- 今後、2019年10月に予定通り消費税率の引き上げがあれば、大きな物価変動は 2019年度~2020年度であると思われるため、その影響による年金目減りは、 2021年度~2024年度に及ぶものと考えられます。 2021年度といえば、先述の改定ルールの変更とも重なるため、改定率が大きな マイナスとなる可能性は十分にあります。 仮にそれが3~4年続いた後には、その期間のマクロ経済スライドの調整率が キャリーオーバーされますので、引き続き高いレベルでの年金給付抑制が続く ことになりそうです。 ●未発動により遠ざかってきたマクロ経済スライドの終了年度と将来世代の憂鬱 毎年度計算されるマクロ経済スライドの調整率は、年金財政の均衡を図ることが できるようになるまでの間行われるもので、例えば 公的年金全体の被保険者の減少率=0.6% 平均余命の伸びを勘案した一定率=0.3% 0.6%+0.3%=0.9%(調整率) このように計算され、毎年度の実績によって結果は上下します。 ・平成28年度 0.7%(適用なし) ・平成29年度 0.5%(適用なし) ・平成30年度 0.3%(適用なし→翌年度以降へキャリーオーバー) ・平成31年度 0.2%(適用は30年度分を加えた0.5%) はじめからコンスタントに適用できていれば、毎年度少しづつのカットで済み 相対的に短期間でマクロ経済スライドの調整期間を終了することができていたの ですが、これまで適用が少なかったために終了年度が先に延び、当初の予定より も多くの年金をカットしなければならなくなりました。 5年に1度行われる財政検証から、調整率と終了年度の見通しを掛けてカットの 割合を計算してみると、 【平成16年(2004年)財政再計算】 調整終了年度 2023年度 平均0.9%×19年=17.1% 【平成21年(2009年)財政検証】 調整終了年度 2038年度(基本ケース) 平均0.9%×29年=26.1% 【平成26年(2014年)財政検証】 調整終了年度 2043~2044年度(労働市場への参加が進むA~E) 平均1.2%×29年=34.8% あくまで単純計算ですが、調整率の適用が遅れた結果、将来世代の年金がより ハードに削られていく様が読み取れます。 また、将来世代の年金は、これまで上げてきたような年金目減りが進行して現状 よりも何割も小さな年金となる上に、年金支給開始年齢の引き上げにより3年5年 (※)といった期間分の年金がごっそり目減りさせられる可能性もあります。 ※5年の引き上げなら、65歳→70歳 寿命が80歳であれば、15年分の5年→3割3分の目減りと同じこと。 特に年金カットのターゲットと思われるボリュームゾーンの団塊ジュニア世代の 年金は、支給開始年齢引き上げを想定しなくとも実質目減りで3割減なのか4割減 なのか、あるいは経済激変でもっと厳しくなるかという状況です。 具体的に、最新データで将来世代の年金がどれだけ目減りする見通しなのか。 今年上半期には発表されるであろう「平成31年財政検証結果」に注目です。
|
|厚生年金繰り下げ受給
|加給年金
|中高齢の特例
|60歳台前半の特例
|定時決定
|育児休業|
| |
|
|任意加入被保険者
|国民年金繰り下げ受給
|保険料免除制度
|国民年金基金
|時効の2年間|
| |
|
年金Q&A |
|公的年金制度と年金問題
|老後の年金生活の実態
|よくある年金の勘違い
|年金と税金|
|
|
年金の手続きその他 |
|年金受給者の手続き
|裁定請求書の書き方と留意点
|年金相談事例
|厚生年金の受給開始年齢|
|