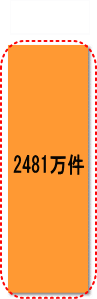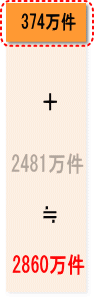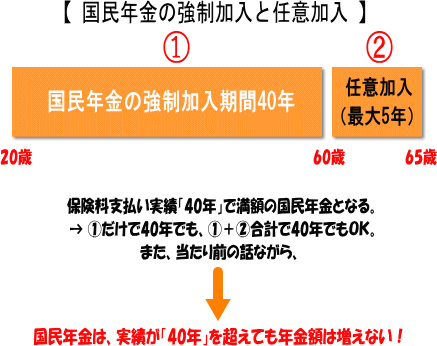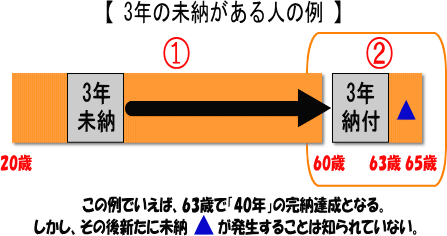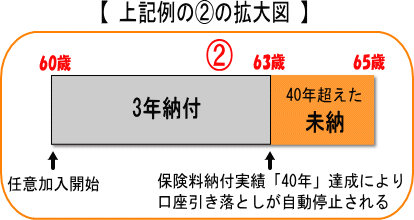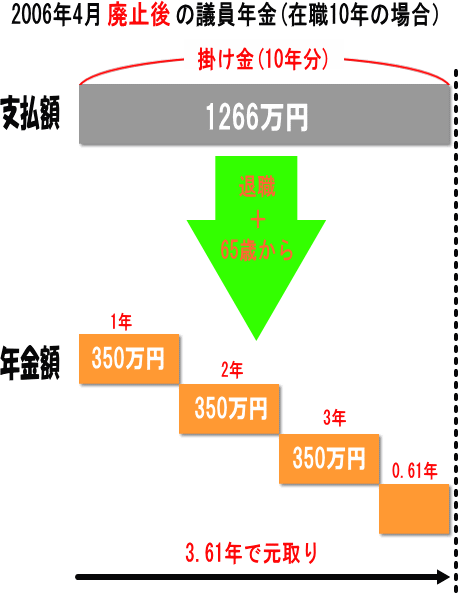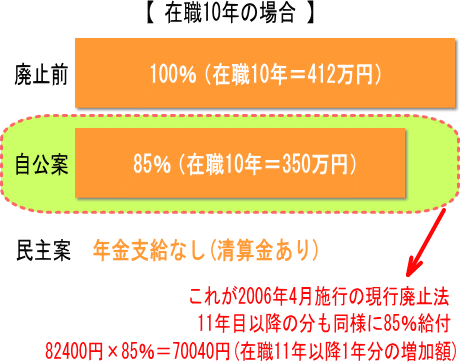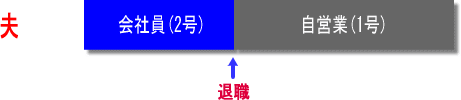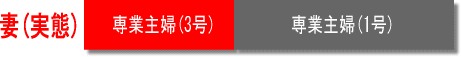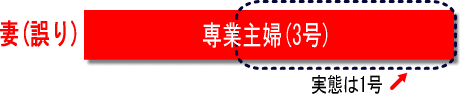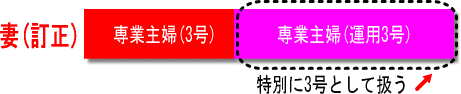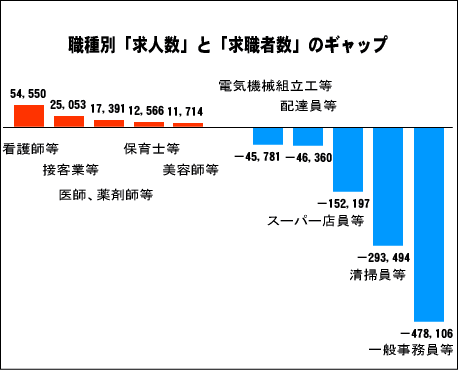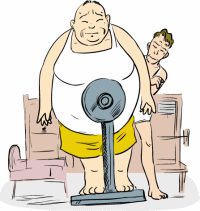国民の年金法はコロコロ変えられるのに、
国会議員年金(廃止法)だけは高値安定のままです。
今回は、キャッチコピー『身を切る改革』が空しく聞こえる
改革なき「廃止後」の国会議員年金を取り上げます。
廃止後も高水準のままの国会議員年金
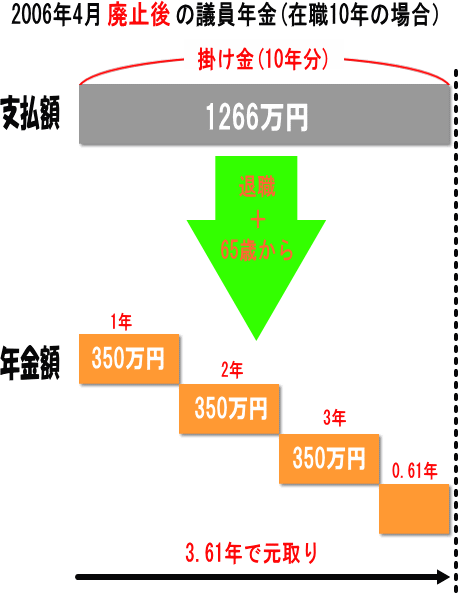
(計算方法については、後述の「民主党議員が将来受け取る国会議員年金額」の注釈欄の所に記載してあります。)
この図は、2012年11月現在はもちろん、まさにこれから落選・引退(以降「退職」)する国会議員が65歳以上であれば受給できる国会議員年金の最低額(在職10年の場合の議員年金額)です。
受給要件は、2006年3月までに国会議員として在職期間10年(10年0か月から10年11か月まで)を有していること。
「あれ、国会議員年金って無くなったのでは?」
そのように思う方も少なくないと思われますが、「廃止法」は、その言葉のイメージとは違い、実際には在職9年11月まで、及び将来の新人国会議員の議員年金を無くすことで「廃止」とされ、2006年3月までの期間で在職10年以上の国会議員の議員年金は、廃止されないばかりか、その削減もわずか15%カットという小さな変更で決着が図られたのです。
在職10年のケースでいうと412万円から350万2000円。
(412万円×85%支給=350万2000円)
このような現職議員の議員年金について、2006年当時野党であった民主党は、独自法案においてで支給しない(0円)と決めていたのですが、数の論理で自民党・公明党の法案が現行の「廃止法」となりました。
【政権交代で政策を実現できる立場にチェンジ】
それから3年が経過した2009年9月。
民主党は、政権交代により与党に立場を変え、晴れて政策決定権を獲得。
これにより「廃止法(国会議員互助年金法を廃止する法律)」を見直す環境は整ったはずなのですが、政権交代後さらに3年が経過した2012年11月現在においても、そのような動きが見られないのです。
もちろん、「廃止法」は決定事項なので、見直さなくても法的にも何ら問題はありません。
しかし、国民の年金法である「国民年金法」「厚生年金保険法」などの改正・改悪ぶりを考えると、国会議員の自分の年金だけ特別扱いとするのは理不尽に思えます。
政権交代前の民主党は、抜本改革で安心できる年金制度にすると言っていたのですが、結局は自公政権からの現行制度の法律改正で対応するやり方を継承。
(民主党政権においても、影響の小さな改正のみならず、今後においては、厚生年金の支給年齢の引き上げや厚生年金基金の廃止など、老後の生活設計が崩壊しかねない法律改正を検討中。)
つまり、民主党の年金法に対する姿勢を見れば、同じく年金の法律である廃止法についても、変える必要性があれば法律改正するのが筋でないかと思うのです。
ついでに言えば、当時も民主党が批判の材料にしていた国会議員年金の財政問題は、2006年当時の公費負担割合72%、そして2012年現在では公費負担100%と変化していますので、この点からも「廃止法」の必要性は高まっていると言えます。
下記図は、在職10年の現職国会議員が将来年金を受給する場合の、2006年当時の旧法、自公案、民主党案の簡易比較です。
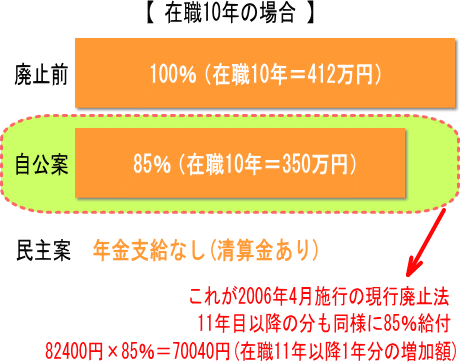
2006年廃止法施行前の民主党の主張
次に、2004年・2005年マニュフェストより、国会議員年金について民主党がどのように主張していたのか、その文言を見てみます。
ここまでならば、「廃止」の定義次第で現行の廃止法をも正当化することが可能ですが、民主党が2006年の独自法案で出してきたものは、現役議員「支給なし」、OB議員「30%支給カット」という自公案との大きなギャップのある具体的な数字でしたので、現行廃止法を見直さないこと自体、時間が経てば経つほど不作為であるとみることができるのです。
下記表は、削減割合を支給割合に直したものです。
| \ | 在職10年以上現職 | OB |
| 自民党・公明党 | 85%支給 | 90%~100%支給 |
| 民主党 | 年金支給なし。
(掛け金の50%を返還)」 | 70%の年金支給 |
※参考外部リンク
自民党松本純衆議院議員HP内
http://www.jun.or.jp/report/2006/060131-honkaigi.pdf
PDF:2ページ目「与党案・民主党案の主な相違点」
さらに、廃止法制定前の討論においては、次のように述べています。
「現職議員はすべて将来の年金受給を放棄します。」
「何より、この国の財政を考え、また、隗より始めよとみずからが痛みを感じる改革が必要だと考えている以上、この程度は当然だと考えています。」
「しかし、与党案では、すでに年金受給資格を得ている現職議員には痛みがほとんどありません。」
(2006年1月31日衆議院本会議第5号速記録より) |
「与党案」とは、自民党・公明党の廃止法案のことです。
法律が施行された2006年4月以降、2012年11月現在においてもなお、この「痛みがほとんどない」議員年金の新規受給が発生し続けており、当然、民主党議員にも議員年金は支給されます。
2006年4月当時から2012年11現在まで継続して民主党に所属している国会議員の議員年金額を見てみます。
民主党議員が将来受け取る国会議員年金額
国会議員年金は、2006年3月までの在職期間で受給額が決定しますので、すでに将来受け取る議員年金の額は確定しています。
年金額の把握の仕方は、「在職期間」を計算した上で、「国会議員互助年金法」に示された計算式より出された答えに「国会議員互助年金法を廃止する法律」で示されている削減額を引きます。
下記表は、民主党議員の「廃止前の年金額」「廃止後の年金額」「民主党の主張していた年金額(0円)」の比較したものですが、全てに0円と表示したのは、当時の民主党の主張と現実との差異をより明確にするためです。
なお、この年金額は、将来受給できる『国会議員年金だけ』の金額ですので、国会議員年金とは別枠で受け取れる「国民年金」「厚生年金」「共済年金」「企業年金」「国民年金基金」「地方議員年金」その他もろもろの年金については、下記の金額に含まれておりません。
在職期間
(~2006年3月) | 廃止前
(~2006年3月) | 現廃止法
(2006年4月~) | 民主党案
(2006年当時) |
| 10年(10年0か月~10年11か月) | 412万円 | 350万2000円 | 0円 |
● 平田健二 参議院議員(10年9か月)
● 小川勝也 参議院議員(10年10か月) |
| 11年(11年0か月~11年11か月) | 420万2400円 | 357万2040円 | 0円 |
| ● 田中眞紀子 衆議院議員(11年7か月) |
| 12年(12年0か月~12年11か月) | 428万4800円 | 364万2080円 | 0円 |
● 枝野幸男 衆議院議員(12年9か月)
● 小沢鋭仁 衆議院議員(12年9か月)
● 玄葉光一郎 衆議院議員(12年9か月)
● 藤村修 衆議院議員(12年9か月)
● 前原誠司 衆議院議員(12年9か月)
● 横光克彦 衆議院議員(12年9か月)
● 海江田万里 衆議院議員(12年10か月)
● 樽床伸二 衆議院議員(12年10か月)
● 仙石由人 衆議院議員(12年11か月) |
| 13年(13年0か月~13年11か月) | 436万7200円 | 371万2120円 | 0円 |
● 池田元久 衆議院議員(13年0か月)
● 北澤俊美 参議院議員(13年9か月)
● 直嶋正行 参議院議員(13年9か月) |
| 14年(14年0か月~14年11か月) | 449万9600円 | 378万2160円 | 0円 |
● 輿石東 参議院議員(14年5か月)
● 柳田稔 参議院議員(14年5か月) |
| 15年(15年0か月~15年11か月) | 453万2000円 | 385万2200円 | 0円 |
● 岡崎トミ子 参議院議員(15年2か月)
● 前田武志 参議院議員(15年9か月)
● 田中慶秋 衆議院議員(15年9か月) |
| 16年(16年0か月~16年11か月) | 461万4400円 | 392万2240円 | 0円 |
● 赤松広隆 衆議院議員(16年2か月)
● 大畠章宏 衆議院議員(16年2か月)
● 岡田克也 衆議院議員(16年2か月)
● 髙木義明 衆議院議員(16年2か月)
● 細川律夫 衆議院議員(16年2か月)
● 松本龍 衆議院議員(16年2か月) |
| 17年(17年0か月~17年11か月) | 469万6800円 | 399万2280円 | 0円 |
| ● 田中直紀 参議院議員(17年9か月) |
| 18年(18年0か月~18年11か月) | 477万9200円 | 406万2320円 | 0円 |
| 19年(19年0か月~19年11か月) | 486万1600円 | 413万2360円 | 0円 |
● 川端達夫 衆議院議員(19年9か月)
● 鳩山由紀夫 衆議院議員(19年9か月) |
| 20年(20年0か月~20年11か月) | 494万4000円 | 420万2400円 | 0円 |
| ● 玉置一弥 衆議院議員(20年8か月) |
| 21年(21年0か月~21年11か月) | 502万6400円 | 427万2440円 | 0円 |
| 22年(22年0か月~22年11か月) | 510万8800円 | 434万2480円 | 0円 |
| 23年(23年0か月~23年11か月) | 519万1200円 | 441万2520円 | 0円 |
| 24年(24年0か月~24年11か月) | 527万3600円 | 448万2560円 | 0円 |
| 25年(25年0か月~25年11か月) | 535万6000円 | 455万2600円 | 0円 |
● 藤井裕久 衆議院議員(25年4か月)
● 中井洽 衆議院議員(25年9か月)
● 菅直人 衆議院議員(25年10か月) |
| 26年(26年0か月~26年11か月) | 543万8400円 | 462万2640円 | 0円 |
| ● 江田五月 参議院議員(26年8か月) |
| 27年(27年0か月~27年11か月) | 552万800円 | 469万2680円 | 0円 |
| 28年(28年0か月~28年11か月) | 560万3200円 | 476万2720円 | 0円 |
| 29年(29年0か月~29年11か月) | 568万5600円 | 483万2760円 | 0円 |
● 中野寛成 衆議院議員(29年5か月)
● 鹿野道彦 衆議院議員(29年5か月) |
| 30年(30年0か月~30年11か月) | 576万8000円 | 490万2800円 | 0円 |
| 31年(31年0か月~31年11か月) | 585万400円 | 497万2840円 | 0円 |
| 32年(32年0か月~32年11か月) | 593万2800円 | 504万2880円 | 0円 |
| 33年(33年0か月~33年11か月) | 601万5200円 | 511万2920円 | 0円 |
| ● 石井一 衆議院議員(33年11か月) |
| 34年(34年0か月~34年11か月) | 609万7600円 | 518万2960円 | 0円 |
| 35年(35年0か月~35年11か月) | 618万円 | 525万3000円 | 0円 |
| 36年(36年0か月~36年11か月) | 626万2400円 | 532万3040円 | 0円 |
| ● 渡部恒三 衆議院議員(36年5か月) |
以下は、表の注釈です。
計算の根拠などを記しています。
議員名および在職期間について |
議員名は、「FRYDAY」2012年4月13日号85ページの表から2012年11月現在も引き続き民主党所属である議員を抜粋し、在籍期間は同表記載のままの転載です。(資料元で「在籍」期間としているところを、当ページでは、資料元の説明箇所を除き「在職」期間と表現しています。国会議員互助年金法では「在職」期間という表現だからです。) |
国会議員年金額の計算について |
年金額についても上記資料元に表示されていましたが、念のため「国会議員互助年金法」および「国会議員互助年金法を廃止する法律」をもとに改めて計算し直しました。 その結果、資料元では在籍10年の議員年金額の計算について、法律の規定通りに350万1999円としている関係上、上記表の年金額よりもすべて1円少ない金額で表示されています。上記表では、在籍10年の議員年金額を350万2000円で計算しています。(差異の原因は、おそらく分数の処理の仕方の違い。) 【廃止前の年金額】 「国会議員互助年金法」第9条(普通退職年金及びその年額)より
『国会議員が在職期間10年以上で退職したときは、その者に普通退職年金を給する。普通退職年金の年額は、在職期間10年以上11年未満に対し退職当時の議員の歳費年額の150分の50に相当する金額とし、10年以上1年を増すごとに、その1年に対し退職当時の議員の歳費年額の150分の1に相当する金額を加算した金額とする。』 そして、「国会議員互助年金法」附則 抄(11)より
『平成6年12月1日以後に退職し、若しくは死亡した国会議員又はこれらの者の遺族に給する互助年金については、当分の間、第9条第2項中「退職当時の議員の歳費年額」とあるのは、「1236万円」とする。ただし、同年11月30日以前における議員の歳費年額(附則第9項本文又は前項本文の規定の適用がある場合は、これらの規定に規定する額)を基礎としてその年額が計算される互助年金については、この限りでない。』 ここまでで、廃止前の年金額が計算できます。 ※外部リンク
国会議員互助年金法
http://law.e-gov.go.jp/haishi/S33HO070.html ★ 廃止前の在職10年の分の年金額 年金額(10年分)=歳費年額×150分の50
=1236万円×150分の50=412万円 ★ 廃止前の在職11年超の年金額(1年あたり) 年金額(11年超の1年分)=歳費年額×150分の1
=1236万円×150分の1=82400円 例えば在職期間15年ならば
412万円+(82400円×5)=453万2000円 次いで、廃止法施行後の年金額の計算です。 【現廃止法による年金額】 「国会議員互助年金法を廃止する法律」第9条(現職国会議員の普通退職年金の年額)より
『(略)これらの規定(略)により計算された金額に100分の85を乗じて得た金額とする。』 ※外部リンク
国会議員互助年金法を廃止する法律
http://law.e-gov.go.jp/announce/H18HO001.html ★ 廃止後の在職10年の分の年金額 年金額(10年分)=歳費年額×150分の50×100分の85
=1236万円×150分の50×100分の85
=412万円×100分の85=350万2000円 ★ 廃止後の在職11年超の年金額(1年あたり) 年金額(11年超の1年分)=歳費年額×150分の1×100分の85
=1236万円×150分の1×100分の85
=82400円×100分の85=70040円 在職期間15年ならば、上記例の計算結果を使い、
453万2000円×100分の85=385万2200円 なお、関連として、掛け金(納付金)について触れておくと、 「国会議員互助年金法」第23条1項より
『国会議員は、毎月、その歳費月額の100分の10に相当する金額を国庫に納付しなければならない。』 歳費月額は歳費年額の「12分の1」ですので「103万円」です。そして、それを100分の10した「10万3000円」が、2006年3月まで月毎月納めてきた納付金ということになります。 さらに、期末手当からの納付もあります。 「国会議員妓女年金法」第23条2項より
『国会議員は、前項に規定する納付金のほか、歳費法第11条の2から第11条の5までの規定による期末手当を受ける月につき、当該期末手当の額(その額に1000円未満の端数がある場合においては、その端数を切り捨てた額)の1000分の5に相当する金額を国庫に納付しなければならない。』 廃止前2006年3月直近では、その金額は約3万円でした。 【ページ最初の掛け金10年分「1266万円」の計算】 以上より、2006年3月まで10年間分の掛け金総額は、
(10万3000円×12月×10年)+(3万円×10年)=1266万円 計算のもととなる「歳費月額」は、過去を遡るほど少ない金額になっており、この計算方法で通用するのは1994年12月から2006年3月までです。 |
最多人数の在職12年組には、大物議員が名を連ねています。
民主党が、マニュフェストで議員年金廃止を訴えたのは2004年からですので、それは、計算上、当該議員が在職10年をクリアして間もなくということになります。
単に、偶然が生んだ状況なのかもしれませんが、政権交代後3年間を見ていると、ついよからぬ勘繰りをしてしまいます。
続きを読む  見直されない「国会議員年金廃止法」と当時の民主党案
見直されない「国会議員年金廃止法」と当時の民主党案