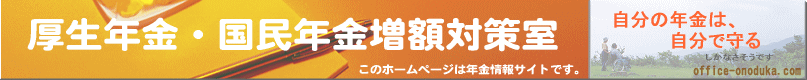
厚生年金・国民年金増額対策室 > 厚生年金増額対策まとめ > 厚生年金増額対策その10「退職改定」
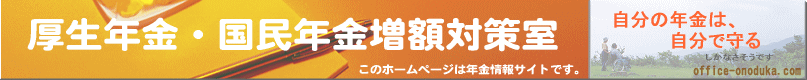
60歳から70歳までの方で、会社員を退職、そしてすぐに再就職という方。
「退職改定」されるので、1ヶ月待った方がよいかもしれません。
年金額が改定されるタイミングは、60歳・65歳・70歳の3回です。
その他は退職した時に再計算され、「退職改定」といいます。
しかし、退職後1ヶ月以内に再就職すると、
年金の世界では継続して厚生年金の被保険者となりますので、
年金額は改定されずにそのままの金額が続くことになります。
1ヶ月を超えて休む、または厚生年金の無い働き方をすれば、
退職時改定によって、それまでの保険料を年金に反映させることができるのです。
いつからいつまで1ヶ月か?
厚生年金の加入者でなくなるのは、会社を退職した翌日ですので、
会社退職日翌日から、次の会社に入社した日までとなります。
1ヶ月を超えてはじめて年金額の再計算となります。
3月31日に退社したら、4月1日が厚生年金でなくなる日ですので、
5月以降に就職すれば大丈夫です。
8月30日に退職→厚生年金被保険者の資格喪失日は8月31日となります。
そして、9月の応当日は31日ですが、9月は30日までですので、
このような場合には民法の第143条(暦による期間の計算)の第2項を用います。
【民法第143条第2項】
「週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、
月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。
ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、
最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。」
つまり、9月の末日の30日が資格喪失後1ヶ月を経過した日となりますので、
9月30日以降の再就職で退職改定が行われることになります。
(この場合、9月分の年金から改定)
(年金額)
第四十三条
2 老齢厚生年金の額については、受給権者がその権利を取得した月以後における被保険者であつた期間は、その計算の基礎としない。
3 被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して
一月を経過したときは、前項の規定にかかわらず、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であつた期間を老齢厚生年金
の額の計算の基礎とするものとし、資格を喪失した日から起算して一月を経過した日の属する月から、年金の額を改定する。
![]() 厚生年金増額対策まとめ
厚生年金増額対策まとめ
1.加給年金
2.中高齢の特例
3.60歳台前半の特例
4.定時決定
5.育児休業
6.在職老齢年金
7.厚生年金繰り下げ受給
8.任意単独被保険者
9.高齢任意加入被保険者
10.退職改定
11.3歳未満の子の養育特例
![]() 国民年金増額対策まとめ
国民年金増額対策まとめ
1.付加年金
2.任意加入被保険者
3.国民年金繰り下げ受給
4.保険料免除制度
5.国民年金基金
6.時効の2年間
7.前払制度(保険料前納)
8.会社員(厚生年金加入)
9.第3号被保険者の空白期間
![]() 年金Q&A
年金Q&A
1.公的年金制度と年金問題
2.老後の年金生活の実態
3.よくある年金の勘違い
4.年金、ここが損得の分れ目
5.国民年金の保険料
6.厚生年金の保険料
7.国民年金保険料の免除
8.年金と税金
9.年金の受給全般
10.老齢基礎年金の受給
11.老齢厚生年金の受給
12.加給年金の受給
13.遺族厚生年金 遺族基礎年金
14.寡婦年金
15.中高齢寡婦加算
16.在職老齢年金QA
17.厚生年金保険への加入
18.国民年金への加入
19.年金の任意加入
20.離婚時の年金分割
21.国民年金基金QA
![]() 国民年金・厚生年金情報通
国民年金・厚生年金情報通
1.厚生年金
2.厚生年金と国民年金
3.国民年金
4.年金生活
5.消えた年金問題
![]() 年金の手続き
年金の手続き
1.年金受給者の手続き
2.裁定請求書の書き方と留意点