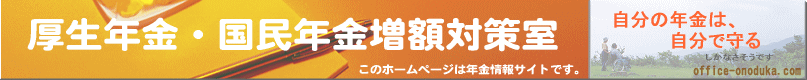
厚生年金・国民年金増額対策室 > 消えた年金記録とは?
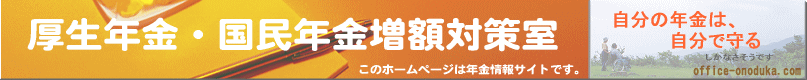
以降当サイトの「消えた年金問題更新一覧」ページはコチラ
(ページ下部が新しい更新となっております。)
宙に浮いた5000万件の年金記録など、社会保険庁のズサンな年金管理が原因で発生した「消えた年金」に次いで、 社会保険庁職員や事業主の故意による厚生年金記録の改ざんである「消された年金」の存在が2008年夏に明らかになりました。
消えた年金よりも悪質で、かつ記録の訂正の困難さが予想される消された年金については、下記ページにて図解入にて解説してあります。
※厚生年金記録の改ざん「消された年金」は、大きく分けて2つの手口があります。
1つが不正な「標準報酬月額の引き下げ」で、消えた年金問題について、詳細がわかるサイト
消えた年金問題騒動により国民の怒りが増大しているにもかかわらず、 年金記録問題の解明については、先に民主党の追及、その後国の調査・公表という流れが多々見られるように思われます。 消された年金問題においても、第三者委員会の厚生年金記録の改ざん認定事例をもとに民主党が追及、そしてその後必要最小限の公表という流れでした。
その他
社会保険事務所に行く前に・・・ちょっとしたまとめです。
テレビ報道などを見ていると、「消えた年金記録が5,000万件」や「宙に浮いた年金記録が5,000万件」と言うのを耳にします。
いったい消えた年金記録とはどういう部分を指すのでしょうか?また、5,000万件という数字を「消えた年金」や 「消えた年金記録」として使うことに間違いはないのでしょうか?
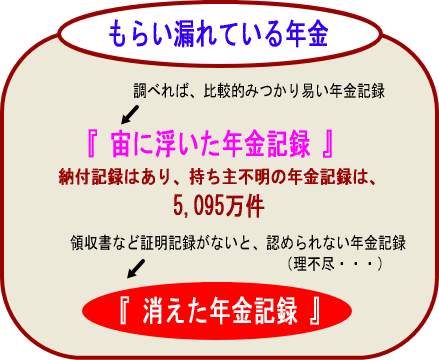
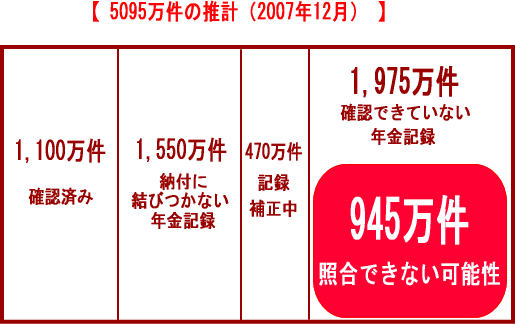
※2008年3月14日厚生労働大臣公表
※2008年3月24日社会保険庁が2025万件を最大2858万件へと修正。
![]() 5,095件の内訳(平成18年6月1日現在)
5,095件の内訳(平成18年6月1日現在) ![]()
| 年齢 | 厚生年金(件数) | 国民年金(件数) |
| ~29歳 | 91,051 | 441 |
| 30~34歳 | 839,128 | 676,059 |
| 35~39歳 | 1,847,523 | 793,558 |
| 40~44歳 | 2,087,273 | 479,389 |
| 45~49歳 | 2,365,136 | 592,710 |
| 50~54歳 | 3,756,391 | 833,144 |
| 55~59歳 | 6,561,810 | 1,222,258 |
| 60~64歳 | 4,567,456 | 794,443 |
| 65~69歳 | 4,357,233 | 1,156,633 |
| 70~74歳 | 3,601,566 | 1,280,747 |
| 75~79歳 | 2,473,400 | 1,230,282 |
| 80~84歳 | 1,808,024 | 832,991 |
| 85~89歳 | 1,266,058 | 605,537 |
| 90~94歳 | 1,110,760 | 516,672 |
| 95~99歳 | 1,010,736 | 267,529 |
| 100歳~ | 1,617,601 | 5,723 |
| 生年月日不明 | 300,675 | 1,166 |
| 合計 | 39,661,821 | 11,289,282 |
| 総合件数 | 50,951,103 | |
| 社会保険庁のコンピュータ上で管理しているもの | |
| 1億426万件 | 基礎年金番号(2006年5月現在) |
| 2万人 | 複数の基礎年金番号を持つ人(2006年10月現在) |
| 5,095万件 |
宙に浮いた状態の年金記録(2006年6月現在) ※厚生年金3,966万件、国民年金1,129万件 ※平成18年12月末現在30歳未満の人には関係のない年金記録。 (平成9年1月の基礎年金番号導入時に20歳未満で、同月前に働いたことがあるが、同月には働いていなかった人を除く) |
| 5,000万件の年金記録の中の欠落記録(平成19年9月10日社保庁公表) | |
| 524万918件 | 消えた年金記録の代名詞となった「5,000万件」の宙に浮く年金記録の中で、氏名がないものが524万918件。 内訳は、氏名のみがない年金記録が493万7396件、生年月日も併せてないものが29万5786件、性別も併せてないものが3927件、生年月日、性別とともにないものが3809件。 |
| 58件 | 上記と同じく、生年月日だけがない年金記録の件数。 |
| 19件 | 上記と同じく、性別だけがない年金記録の件数。 |
| 三鷹の社会保険業務センター等、倉庫にあるとされる年金記録(マイクロフィルム) | |
| 1,430万件 |
1954年(昭和29年)3月以前に厚生年金を脱退し、社会保険庁のコンピューターに入力されていない厚生年金の旧台帳(1987年(昭和62年)3月現在)の年金記録。
※そのうち33万件は持ち主特定困難なもの。(被保険者の記録と旧台帳の記録とで名前や生年月日などの情報が異なる「別人台帳」が26万件、 旧台帳に記入漏れがあったり判読不能だったりしている「事故台帳」が7万件) ※平成19年現在で概ね68歳以下の人には関係のない年金記録。さらに、昭和29年3月以前の厚生年金は対象とする業種の幅が限られており、 対象業種である鉱業、工業、運輸、電力、金融等以外の従業員にも関係がない年金記録であるといえます。 |
| 36万件 | 船員保険の人の年金記録(1999年3月現在) |
| 市役所・区役所等 | |
| 191市区町村 |
国民年金の手書名簿を破棄(2007年5月現在) ※1636市町村は保管。 |
| その他 | |
| 55人 |
年金記録が消えていたが、領収証があって年金記録が加算された人 ※2006年8月~12月 |
| 180人 |
年金記録が消えていたが、領収証があって年金記録が加算された人 ※2007年1月~3月に受け付けた115万件を調査(2007年9月3日社保庁公表)。 証拠書類の内訳は「領収書130件」「年金手帳75件」「領収済証明書7件」(重複あり) |
| 1,541人 |
年金記録が消えていたが、領収証があって年金記録が加算された人 ※2007年9月末時点(2008年3月22日社保庁公表)。 |
| 2万635人 |
「保険料を払った」という申立てに対して認められなかった人 ※2006年8月~2007年3月 |
| 22万人 | 年金記録の間違いを社保庁に訂正させた人(2001年度から6年間) |
| 9万3000人 |
年金の請求自体が遅れたために、一部時効となった年金がある人 ※1999年~2003年度、厚生労働省推計|時効総額1155億円 |
| 25万人 |
年金の支給漏れのために、一部時効となった年金がある人 ※推計額950億円 |
| 1964年前 | 社会保険庁が年金の記録ミス多発を認識していた時期。1964年9月1日付の社保庁業務課長名の通知に「いぜんとして台帳番号確認誤りによる記録事故が多数発見されており」 との記述があるほか、1967年に社会保険庁年金保険部業務課(当時)がまとめた内部資料「機械化十年のあゆみ」でも記録ミス多発を指摘。 そして社会保険庁年金保険部が1987年に発行した内部資料「三十年史」では、同一人の記録が複数で管理されることにより年金記録が宙に浮く可能性を指摘している。 |
| 3千万件 |
社会保険庁のコンピューター上にある国民年金の納付記録1億3900万件のうち、市町村並びに社会保険庁に原簿となる台帳が存在しないとされる件数。
※国民年金の台帳が残っていた市町村は1636で、2007年5月31日現在の集計では紙台帳3057万件、マイクロフィルム2313万件、磁気媒体3660万件、合計9030万件となっている。 国民年金名簿未保管200旧市町村名 |
| 181万件 | 共済年金で基礎年金番号に統合されていない年金記録の件数。 内訳は、国家公務員共済67万件、地方公務員共済68万件、私学共済46万件。 すべて1997年に基礎年金番号が導入された時点で、すでに退職した職員らの記録。 |
| 83万件 | 社会保険庁が1959年から1982年ごろにかけ、厚生年金の記録の原簿にあたる手書きの「被保険者台帳」を、マイクロフィルム化や磁気テープ化せず、違法に廃棄していた件数。 83万件のうち71万件は本人の年金額の確定後に捨てたものだが、12万件については内訳が不明。 |
|
99件 3億4千万円 | 社保庁と市町村職員の年金の不正受給・年金保険料の着服の総計。保険料着服に絞れば合計71件2億3400万円、このうち市町村は49件2億77万円。 |
| 945万件 | 年金記録を偽名で届け出た人や社保庁の入力ミスなどにより、宙に浮いた年金記録の中の特定困難とされている1975万件の年金記録の中でも、最も特定することが困難とされている 年金記録の件数。 |
| 2,823万円 | 96歳の男性に支払われた、時効の未払い年金分の金額。 年金時効撤廃特例法に基き、過去5年を越える部分の年金についても遡って受給できるようになった。 当男性の場合には、50歳まで加入していた厚生年金30年分以上が支給漏れとなっていた。(2008年1月17日の日本テレビCS放送番組にて民主党長妻議員が明らかにしたもの。) |
| 2,750万円 | 85歳の男性に支払われた、時効の未払い年金分の金額。 船員保険の年金受給者で、72歳の時に記録漏れが判明したものの、年金時効撤廃特例法がなかった当時、 5年の時効が適用されて年金受給開始年齢の55歳から67歳ころまでの約12年間分の年金が支給されていなかった。 (2007年12月17日読売新聞:社会保険庁公表) |
| 不明 | 支給漏れに気が付かない、隠れ被害者 |
上記図のように「消えた年金記録」は、言葉通りの説明ならば、物理的に国に保管されているべき年金データが消失してしまっている年金です。
一方で、国に年金データが残されており、持ち主のわからない年金記録が5,000万件ありますが、これも消えた年金記録と言うことも、間違いではありません。
これらをまとめると、以下のようになります。
![]()
国に保管されているべき年金記録で、破棄または消失した年金記録のことです。国が証明しようにも証明できず、 受給者もいまさら領収書が存在するわけもなく、年金漏れ解消の最も困難な部分です。
![]()
国にあるといわれている5,000万件の宙に浮いた年金の中で、 名前・生年月日・性別などの記載ミスや破損によって照合が困難で、事実上持ち主が判明できない年金記録です。
また、コンピュータ上には年金記録がない場合で、書面の台帳には記録が残っているものについても、事実上の消えた年金記録があります。 なぜなら、台帳等コンピュータに入っていない年金記録も、整然と管理されているわけではないからです。
もっと言えば、台帳等にあるかもしれない年金記録でも、そこまで調べる手続を踏まなければ、探すことすらなされないのです。
![]()
私たち国民から見れば、もらい漏れている年金は名前などまったく関係なく、すべてが「消えた年金記録」です。 そういう意味で、5,000万件が消えた年金ということも、決して間違いではありません。
最終的には会社名が書かれた古いメモが見つかったので年金記録を統合できましたが、
記憶力が落ちた方にとっては、簡単な年金記録の統合作業も非常に困難になりうるだろうと感じたケースでした。
対話風ですので、要点がつかみにくいかもしれません。
「厚生年金の年金記録が抜けている!!」
基本的に、年金手帳や厚生年金被保険者証がなく、個々の厚生年金被保険者番号が分からない場合、年金記録が宙に浮く可能性はグンと高まります。
さらに「名前」や「生年月日」などで年金記録のこん跡が出てこなかった場合は、年金記録を見つけるのは困難になります。
あとは、台帳等照合調査をゆだねる他ありません。
そして、結果として年金記録が見つからなかったとき、国側の年金記録の管理ミスなのか、 はては私たち年金受給主側の思い違いや勘違いなのかは、はっきり言って分かりません。 くやしい限りですが、年金のしくみの上では年金を請求するときに年金手帳なり厚生年金の番号なりを持参して請求することを前提としているため、 厚生年金の一部が抜けていると言うようなケースは山のように存在していると思われます。
ここでは、社会保険審査会の裁決の中から、厚生年金の記録が認められない、または途中まで厚生年金が年金漏れになっていた事例をご紹介いたします。
破棄・消失された年金記録の具体的な件数はわかりませんが、目安となりうる数字はあります。 平成18年8月21日から12月末までの約4ヶ月に社会保険庁が実施した年金相談において、 86件が社会保険庁に年金記録が残っていない中、本人による領収書持参で年金記録が見つかりました。 ちなみに、そのうち55件に関しては、最後の最後まで国に年金記録がなかったということです。
しかし、平成18年8月21日から平成19年3月2日までに「自分はもっと年金記録が多いはずだ」として申立てを行ったのは実に1万7,204人。 86件以外の方々は、領収書など証明できるものがなく、結局年金記録を訂正することはできませんでした。
ここで、一つの事実が分かります。 「年金記録が存在しません」とされた受給権者の中で領収証があったために、年金記録が加算された人が86件。 そしてその後、政府野党の国会での追及によって「やっぱり記録があった」とされた人を除くと、最終的に年金記録が存在しなかった人は55件。
つまり、きちんと探せば「無い」とされていた年金記録の中にも、存在する年金記録があるということです。その数なんと3割。
私たち国民一人ひとりの申出では動かないのに、政治家が追求すると事実が出てくる。
なんともやりきれなさを覚えます。
効果的な対策は?
税務署に社会保険料控除の記録は残されていないか、公共職業安定所に、過去の勤務記録は残されていないか (「テープ落ち」といい、古すぎるデータは出てきませんでした)、市役所・区役所に何らかのデータは残されていないか、 何か決め手になりそうな対策があればそれが一番よいのですが、実際には「客観的な証明資料」は、ほとんどないと思われますので、その他の証明方法が「消えた年金対策」 のポイントになってくると思います。
そして、なんら証明するものがない場合、当時の記憶と状況の説明において判断することになるかと思われますが、 本当に保険料を納めた人と、そうでない人の区別はどうなるのか?真正の場合と、本人の勘違いのケースを見極めることはできるのか? 本当に保険料を納めた人でも、記憶力の点で具体性や説得力に欠ける場合には認めてもらえないのか?その線引きはどうするのか? どの窓口でも、等しく公平に判断してもらうことはできるのか?
本当ならば、ある程度の説得性があれば、申し出たすべての年金を支払うのが筋だと思うのですが、 現実的にはどうしても一定の線引きは必要になってきます。
例えば、あるタクシー会社の例ですが、社会保険に入る「勤務A」という身分、または、手取りは増える反面社会保険には入らない「勤務B」という身分を選択できるような場合、 当時厚生年金に入らない「勤務B」を選んでいたにもかかわらず、一緒に働いていた人が厚生年金をもらっているために自分も厚生年金に入っていたはずだと信じ込んでいた、 ということもありましたが、これなどは、会社が現存していたために確認できたものの、会社が倒産していた場合には、選別する基準が一切無いとなると、間違って厚生年金を 支給することとなりかねません。
また、倒産した会社で、単純に社会保険に加入していなかった場合や、短期の雇用形態で社会保険に加入していなかった場合、または、社員に近いパート勤務や請負などで働いていて 厚生年金に加入していなかった場合などでも、年金の知識がなければ「厚生年金に入っていたはずだ」とうことになりやすいと思われます。
しかし、だからと言って本来もらえるべき人までも救済されなくなることは許されませんので、 走りながら認定基準を策定・運用、そして裁判の判例のように認定基準を確立していくしかないように思います。
社保庁の労働組合の「あの」覚書
キーボード1日5000タッチ~等、自治労国費評議会の事務局長と社保庁総務課長との間で取り交わされた「覚書(確認事項)」
厚生労働省のホームページで見ることができます。
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/09/s0908-4.html「資料1-7」
消えた年金記録関連ニュース
記事元|日経新聞(NIKKEI NET)
![]() 厚生年金増額対策まとめ
厚生年金増額対策まとめ
1.加給年金
2.中高齢の特例
3.60歳台前半の特例
4.定時決定
5.育児休業
6.在職老齢年金
7.厚生年金繰り下げ受給
8.任意単独被保険者
9.高齢任意加入被保険者
10.退職改定
11.3歳未満の子の養育特例
![]() 国民年金増額対策まとめ
国民年金増額対策まとめ
1.付加年金
2.任意加入被保険者
3.国民年金繰り下げ受給
4.保険料免除制度
5.国民年金基金
6.時効の2年間
7.前払制度(保険料前納)
8.会社員(厚生年金加入)
9.第3号被保険者の空白期間
![]() 年金Q&A
年金Q&A
1.公的年金制度と年金問題
2.老後の年金生活の実態
3.よくある年金の勘違い
4.年金、ここが損得の分れ目
5.国民年金の保険料
6.厚生年金の保険料
7.国民年金保険料の免除
8.年金と税金
9.年金の受給全般
10.老齢基礎年金の受給
11.老齢厚生年金の受給
12.加給年金の受給
13.遺族厚生年金 遺族基礎年金
14.寡婦年金
15.中高齢寡婦加算
16.在職老齢年金QA
17.厚生年金保険への加入
18.国民年金への加入
19.年金の任意加入
20.離婚時の年金分割
21.国民年金基金QA
![]() 国民年金・厚生年金情報通
国民年金・厚生年金情報通
1.厚生年金
2.厚生年金と国民年金
3.国民年金
4.年金生活
5.消えた年金問題
![]() 年金の手続き
年金の手続き
1.年金受給者の手続き
2.裁定請求書の書き方と留意点