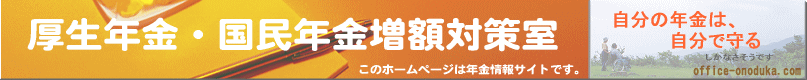
厚生年金・国民年金増額対策室 > 厚生年金増額対策まとめ > 厚生年金増額対策その11「3歳未満の子の養育特例」
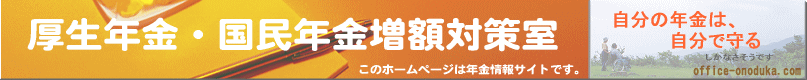
厚生年金増額対策その5「育児休業」でも触れた「3歳未満の子の養育特例」 を、このページでは詳細にお話しします。
3歳未満の子の養育特例(3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例)は、3歳未満の子を養育する厚生年金の被保険者が、 3歳未満の子どもを育てている期間に給料(標準報酬月額)が下がっても、将来の年金額は、子供を育て始める直前の標準報酬月額で計算するしくみのことです。
関連:標準報酬月額とは?
関連:厚生年金の計算で使う平均標準報酬月額とは?
平成17年4月から始まった制度ですが、平成17年4月以前に生まれた子でも3歳になっていなければ利用できます。
もしもこの3歳未満の子の養育特例を利用しなかった場合、同じように3歳未満の子を養育している期間に標準報酬月額が下がったケースにおいては、 その下がった標準報酬月額をもって将来の厚生年金が計算されます。
この3歳未満の子の養育特例は「本人からの申出」により利用できる制度です。届出をすれば年金が減らないのに、届出をしないばかりに将来もらえる年金が減る。つまりは 単に損をしてしまうだけになってしまいます。
「本人からの申出」があった場合には、会社が「厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書」を社会保険事務所へ届出ることになっています。届出には 次の添付書類が必要です。
届出漏れでも会社に責任なし
あくまで会社員等の「本人からの申出」が要件ですので、制度を利用できなかった時に「会社が教えてくれれば届出をしたのに!」と憤慨しても会社に責任は問えません。
3歳未満の子の養育特例で、届出をしていなかった場合、2年間であれば遡って適用することができます。これは、退職後であっても申出が可能です。 (その場合は直接社会保険事務所に届出書を提出)
3歳未満の子の養育特例は、妻に限らず夫も対象となります。妻が専業主婦である夫でも対象ですし、共働きをしているならば夫婦共に申し出をすることができます。
この制度は、育児休業を取らなくても利用できます。
給与(標準報酬月額)が下がる理由は次のようなものですが、特に理由が限られているものではありません。
3歳未満の子どもがいて新たに就職する場合
3歳未満の子どもがいて新たに就職する場合、その前月に厚生年金保険の被保険者でなかった場合は、 その前月以前1年以内に厚生年金保険の被保険者であったことが必要となります。
この3歳未満の子の養育特例の届出は、標準報酬月額が下がらなくても提出することができます。 よって、3歳未満の子供がいる人等についての届出 (厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書(社保庁HP)はとりあえず行なっておくのが安心です。
(3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例)
第26条
3歳に満たない子を養育し、又は養育していた被保険者又は被保険者であつた者が、厚生労働省令で定めるところにより社会保険庁長官に申出
(被保険者にあつては、その使用される事業所の事業主を経由して行うものとする。)をしたときは、当該子を養育することとなつた日
(厚生労働省令で定める事実が生じた日にあつては、その日)の属する月から次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日の属する月の前月までの各月のうち、
その標準報酬月額が当該子を養育することとなつた日の属する月の前月(当該月において被保険者でない場合にあつては、当該月前1年以内における被保険者であつた月の
うち直近の月。以下この項において「基準月」という。)の標準報酬月額(この項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬月額が標準報酬月額とみなされてい
る場合にあつては、当該みなされた基準月の標準報酬月額。以下この項において「従前標準報酬月額」という。)を下回る月(当該申出が行われた日の属する月前の月にあつては、
当該申出が行われた日の属する月の前月までの2年間のうちにあるものに限る。)については、従前標準報酬月額を当該下回る月の第43条第1項に規定する平均標準報酬額の
計算の基礎となる標準報酬月額とみなす。
2 前項の規定の適用による年金たる保険給付の額の改定その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
![]() 厚生年金増額対策まとめ
厚生年金増額対策まとめ
1.加給年金
2.中高齢の特例
3.60歳台前半の特例
4.定時決定
5.育児休業
6.在職老齢年金
7.厚生年金繰り下げ受給
8.任意単独被保険者
9.高齢任意加入被保険者
10.退職改定
11.3歳未満の子の養育特例
![]() 国民年金増額対策まとめ
国民年金増額対策まとめ
1.付加年金
2.任意加入被保険者
3.国民年金繰り下げ受給
4.保険料免除制度
5.国民年金基金
6.時効の2年間
7.前払制度(保険料前納)
8.会社員(厚生年金加入)
9.第3号被保険者の空白期間
![]() 年金Q&A
年金Q&A
1.公的年金制度と年金問題
2.老後の年金生活の実態
3.よくある年金の勘違い
4.年金、ここが損得の分れ目
5.国民年金の保険料
6.厚生年金の保険料
7.国民年金保険料の免除
8.年金と税金
9.年金の受給全般
10.老齢基礎年金の受給
11.老齢厚生年金の受給
12.加給年金の受給
13.遺族厚生年金 遺族基礎年金
14.寡婦年金
15.中高齢寡婦加算
16.在職老齢年金QA
17.厚生年金保険への加入
18.国民年金への加入
19.年金の任意加入
20.離婚時の年金分割
21.国民年金基金QA
![]() 国民年金・厚生年金情報通
国民年金・厚生年金情報通
1.厚生年金
2.厚生年金と国民年金
3.国民年金
4.年金生活
5.消えた年金問題
![]() 年金の手続き
年金の手続き
1.年金受給者の手続き
2.裁定請求書の書き方と留意点