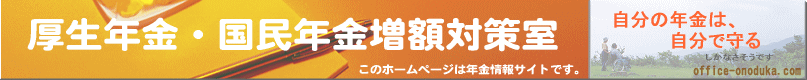
厚生年金・国民年金増額対策室 > 厚生年金受給開始年齢 > 昭和30年4月2日~32年4月1日生まれの方の年金(男性)についての解説。
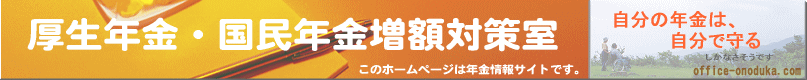
◎原則……厚生年金や共済年金の加入期間がある方は、
62歳から65歳まではその加入期間に対応した年金が受け取れます。
そして65歳からは国民年金の受給開始年齢になりまして、厚生年金等と併せた金額を受け取ることが出来ます。
原則25年以上何らかの公的年金に加入していたことが条件です。
それでは62歳から65歳までの定期年金と、65歳からの生涯年金の2つに分けて説明致します。
なお、厚生年金の説明=共済年金の説明として話を進めますが、その違いは厚生年金でいう2階部分のさらに上に3階部分が付くということです。
これを職域加算と言いますが、これ以外の仕組みは厚生年金と同じです。
それでは説明に入ります。
①62歳~65歳になるまで
| 【2階部分】厚生年金・共済年金(現役時代の収入に対応した年金です) |
| 【1階部分】65歳になるまで支給なし |
国民年金からの支給
国民年金は65歳になるまでは出ません。
厚生年金・共済年金からの支給
62歳から65歳になるまでは2階部分だけの厚生年金が出ます。
2階部分というのは、加入した期間の収入の違いによって年金額に差が出る部分のことです。
つまりAさんとBさんが同じ加入期間なら、収入の多かった人のほうが年金額が多くなるのです。
仕組みはこの辺にして、繰り返しますが昭和30年4月2日~昭和32年4月1日生まれの方は62歳になったらその月から厚生年金の2階部分だけの年金が出始めるのです。
ちなみにわずかな期間しか会社員や公務員をやっていなかったという方も、1年以上その期間があり、国民年金の加入期間と併せて原則25年以上あればその分は年金が出ます。
②65歳~生涯もらう年金
| 厚生年金・共済年金(経過的加算) |
| 【2階部分】厚生年金・共済年金(現役時代の収入に対応した年金です) |
| 【1階部分】国民年金(加入期間のみに対応した老齢基礎年金) |
国民年金からの支給
国民年金は65歳になったらその月から一生涯支給されます。
国民年金は"保険料"の額が決っています。"年金額"も収入に関係なく加入期間だけで計算されます。
ちなみに20歳から60歳までの40年間を全て何らかの公的年金に加入され、保険料を納めていた方は国民年金からは年額約80万円受給できます。
会社員でも公務員でも自営業でも、何らかの形で保険料を納めていればOKです。
厚生年金・共済年金からの支給
まず65歳まで受給できる2階部分の厚生年金が、引き続き65歳以降一生涯支給されます。
それと、厚生年金から『経過的加算』という年金がプラスされて支給されます。
では、経過的加算とはどういうものでしょう。
国民年金は20歳から60歳までの加入期間を元に計算されますが、厚生年金は20歳未満でも60歳以後も加入期間に入ります。
つまり厚生年金の加入期間には入るけれど、国民年金の年金を計算する期間には入らない期間が働き方によっては出てきます。
例えば高校を卒業してすぐに会社員をされている方などは20歳までの期間は国民年金の年金額を計算する対象期間とはされません。
そこで、そのように国民年金の計算から除外された期間は経過的加算として厚生年金から支給してくれるのです。
少しわかりづらかったですね。
ただ年金額から言えば主要な部分ではなく、わからないからといってそう気にすることはないと思います。
■62歳から65歳になるまでの年金。
厚生年金が出ます。同じ期間でも収入によって差が出てくるという2階部分の年金のことです。
■65歳からの年金。
国民年金から支給される20歳から60歳までの公的年金加入期間によって計算される"老齢基礎年金"=1階部分
厚生年金から支給される加入期間と収入によって差が出てくる2階部分の年金
厚生年金から支給される経過的加算
*なお、厚生年金等に原則20年以上加入している方で、国民年金が出始めるときなどに65歳未満の配偶者がいる、18歳未満の子供が居るなどの 条件に合う方は約20万円の「加給年金」が加算されます。その上対象となる方が65歳未満の配偶者であって、65歳になるまでは「特別加算:昭和18年4月2日以降生まれの方で約18万円」が支給されます。
以上が受給開始年齢ですが、あくまで原則ですし、表現もわかり易さを優先して正確でないものも使っております。
例えばここで言う62歳~65歳までの年金は「特別支給の老齢厚生年金」と言いまして、2階部分は収入に比例しているということから「報酬比例部分」と呼びます。
また、公的年金の加入期間は25年ないと年金が出ないというのは最近は浸透してきた話ですが、ほんの一例として例えば会社員や公務員期間を合算した期間が24年あるという昭和30年4月2日~昭和32年4月2日生まれの方は、それだけで年金受給資格を得るということなど、 細かく例外も設定されています。
![]() 厚生年金増額対策まとめ
厚生年金増額対策まとめ
1.加給年金
2.中高齢の特例
3.60歳台前半の特例
4.定時決定
5.育児休業
6.在職老齢年金
7.厚生年金繰り下げ受給
8.任意単独被保険者
9.高齢任意加入被保険者
10.退職改定
11.3歳未満の子の養育特例
![]() 国民年金増額対策まとめ
国民年金増額対策まとめ
1.付加年金
2.任意加入被保険者
3.国民年金繰り下げ受給
4.保険料免除制度
5.国民年金基金
6.時効の2年間
7.前払制度(保険料前納)
8.会社員(厚生年金加入)
9.第3号被保険者の空白期間
![]() 年金Q&A
年金Q&A
1.公的年金制度と年金問題
2.老後の年金生活の実態
3.よくある年金の勘違い
4.年金、ここが損得の分れ目
5.国民年金の保険料
6.厚生年金の保険料
7.国民年金保険料の免除
8.年金と税金
9.年金の受給全般
10.老齢基礎年金の受給
11.老齢厚生年金の受給
12.加給年金の受給
13.遺族厚生年金 遺族基礎年金
14.寡婦年金
15.中高齢寡婦加算
16.在職老齢年金QA
17.厚生年金保険への加入
18.国民年金への加入
19.年金の任意加入
20.離婚時の年金分割
21.国民年金基金QA
![]() 国民年金・厚生年金情報通
国民年金・厚生年金情報通
1.厚生年金
2.厚生年金と国民年金
3.国民年金
4.年金生活
5.消えた年金問題
![]() 年金の手続き
年金の手続き
1.年金受給者の手続き
2.裁定請求書の書き方と留意点