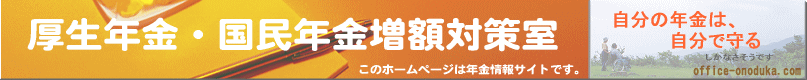
厚生年金・国民年金増額対策室 > 裁定請求書の書き方と留意点 > 国民年金老齢年金裁定請求書[旧](様式第191号)
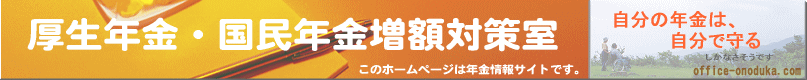
旧国民年金法による老齢年金(今で言えば老齢基礎年金のような位置づけ)の適用を受ける人は、大正15年4月1日以前に生まれた人、 または昭和61年3月31日において旧厚生年金保険法・旧船員保険法による老齢年金もしくは共済組合が支給する退職(減額退職) 年金(昭和6年4月1日以前に生まれた人に支給されるものに限る)の受給権を有している人です。
また、国民年金が誕生したのは昭和36年4月1日であり、その当時すでに中高齢の人たちにとっては年金に入りたくても入れない状況にあったことから、 原則は年金の受給資格期間を25年としながらも、生年月日に応じて受給資格期間等において特例規定が設けられています。
昭和5年4月1日以前生まれの人の旧国民年金の老齢年金の受給資格期間は、 大正5年4月1日以前生まれの人が10年、大正5年4月2日生まれから大正6年4月1日以前生まれが11年、 大正6年4月2日生まれから大正7年4月1日以前生まれが12年・・・昭和4年4月2日生まれから昭和5年4月1日以前生まれが24年、 昭和5年4月2日以降生まれが25年というように、生年月日が1年後れるごとに受給資格期間も1年ずつ長くなる仕組みになっています。 なお、受給資格期間は、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算したものです。
5年年金とは、昭和39年4月2日から明治44年4月1日までの間に生まれた人を対象とした年金で、昭和45年1月1日から昭和45年6月30日まで、または昭和48年10月1日から昭和49年 3月31日までに5年間被保険者となった人は、保険料納付済期間が5年に達したあとに65歳に達したとき、もしくは65歳に達したあとに保険料納付済期間が5年に達した時に 老齢年金を受けられるというものです。
大正5年4月1日以前生まれの人は、保険料納付済期間1年以上、かつ保険料免除期間と合算した期間が4年1ヶ月~7年1ヶ月以上あれば、特例的に老齢年金を受給できます。 また、保険料納付済期間が1年未満で、保険料免除期間と合算した期間が4年1ヶ月~7年1ヶ月以上の期間である時には、老齢福祉年金が支給されます。
下記表の記入事項の数字「1,2,3・・・」や、カタカナ「ア,イ,ウ・・・」は、当該「国民年金老齢年金裁定請求書[旧]」 に記入してあるものに対応しています。
| 記入事項 | 国民年金老齢年金裁定請求書[旧]の書き方と留意点 |
|---|---|
| 1(請求者の基礎年金番号) | 基礎年金番号は、 基礎年金番号通知書(ハガキ形式の薄い青のしましま模様)や年金手帳に記してあります。 |
2(生年月日) | 年号は、該当する『文字』を丸で囲みます。生年月日の数字が一桁の時には、「04」月や「05」日のように、十桁欄にゼロ「0」を記入します。 |
3,7,10,11のフリガナ | カタカナ共通の留意点は「現代かなづかいを使用」「ヰ、ヱはイ、エと記入」「なまり(地域的発音)は使用しない」
「カタカナ、ひらがな、変体がな、外国文字にもカタカナを付する」以上の4つ。
|
17(請求者の氏名)の印 | 受給権者自ら署名する場合には、押印不要(本人の自署でない場合には、本人印が必要。) |
支払機関 | 「1,金融機関」か「2,郵便局」のいずれかを選択し、正式な名称で記入する。 金融機関の「銀行・金庫・信組」、「本店・支店・出張所」、「信連・信漁連・農協・漁協」、「本所・支所・本店・支店」および、郵便局の「郡・市」は該当する文字を丸で囲む。 農協を選択する場合には、年金の振込みが可能なところでなければならない。 「預金通帳の口座番号」または「郵便振替口座の口座番号」は、選択した機関の預金通帳の記号番号について正確に記入する。 金融機関を希望した時には、その金融機関で預金通帳の記号番号についての証明を受ける。 郵便局を希望した時は、9の郵便局自体の郵便番号も記入。 |
13(1.支給繰上げの請求をする、2.支給繰下げの申出をしていた) | 支給繰上げを請求していた人、支給繰下げの申出をしていた人だけが、該当する事項を丸で囲む(今はもう、繰上げの話は出てこないのではないでしょうか。) |
イ(次のいずれかの国民年金を受けていますか)、ウ(受けている場合はその年金名を丸で囲む) | 「障害年金、母子年金、準母子年金、旧寡婦年金、障害基礎年金(旧障害福祉年金)、遺族基礎年金(旧母子福祉年金)、 遺族基礎年金(旧準母子福祉年金)、障害基礎年金、寡婦年金、障害基礎年金(20歳前障害)、 遺族基礎年金」のうち、該当する国民年金を受けているものがあれば丸で囲む。 なければ、イの「2.受けていない」を丸で囲む。 |
オ(次のアからクまでの制度の組合員であったことにより旧国民年金の老齢年金を 受けることができた場合は、どの制度の組合員でしたか) | 「ア.旧陸軍共済組合、イ.旧海軍共済組合、ウ.朝鮮総督府逓信官署共済組合、エ.朝鮮総督府交通局共済組合、 オ.台湾総督府専売局共済組合、カ.台湾総督府営林共済組合、キ.台湾総督府交通局逓信共済組合、ク.台湾総督府交通局鉄道共済組合」のうち、該当する事項を丸で囲む。 |
カ(国民年金制度以外の公的年金制度から年金を受けていますか。)キ(受けているときは、その公的年金制度の名称および年金証書の 基礎年金番号・年金コードを記入して下さい) | 国民年金制度以外の公的年金制度から年金を受けているときは、その公的年金制度の名称および年金証書の基礎年金番号・年金コードを 記入する。なお、共済組合等から年金を受けている場合は、「制度の名称」欄に年金の支払いを行っている機関の名称、「年金証書の基礎年金番号・年金コード等」欄に その年金の種類および年金証書の記号番号を記入する。 |
ク(旧住所) | 現在の住所が最後に被保険者でなくなった当時の住所と異なる場合、その旧住所を記入する。現住所が、最後に被保険者でなくなった住所 と引続き同じ場合には記入の必要はない。 |
裁定請求書(国民年金老齢年金裁定請求書[旧])の提出と共に添付する書類等は次の通りです。
(人により、提出すべき添付書類は異なります。)
|
【1】国民年金手帳
|
裁定請求書(国民年金老齢年金裁定請求書[旧])の提出先は、住所地の市区町村です。
|
|厚生年金繰り下げ受給
|加給年金
|中高齢の特例
|60歳台前半の特例
|定時決定
|育児休業|
| |
|
|任意加入被保険者
|国民年金繰り下げ受給
|保険料免除制度
|国民年金基金
|時効の2年間|
| |
|
年金Q&A |
|公的年金制度と年金問題
|老後の年金生活の実態
|よくある年金の勘違い
|年金と税金|
|
|
年金の手続きその他 |
|年金受給者の手続き
|裁定請求書の書き方と留意点
|年金相談事例
|厚生年金の受給開始年齢|
|